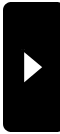2000年02月06日
杉浦清石 ロマン街道塩の道 6
「お梅ばぁちゃんの話」 其の五 天災
又聞きの話ですが「おらがとっっあんの友達でよー」と語ってくれた話があります。 とっっあんの仲の良い友達でボッカやっているのがいました。 その頃のボッカは必ず二人以上で歩くのがキメ(取り決め)で、荷の少ないときはおらとこのとっっあんといつも一緒です。
ボッカの楽しみといやー(云えば)何てったって祭りだあーね。 大所のハズレで峠に掛かる所に駄菓子屋がポツンとあってな。 荷かついて峠越えて行った帰りにいつも寄って茶のんで休むところさ。
ここのば様(おばあさん)の亭主出稼ぎでけえって(帰って)こねえ。 行方知れずでさ。 娘一人あって、 器量好しだでボッカ仲間で評判で寄るもん多かった。 イチさも(イチは友達の呼び名)惚れてただーな。 その娘がさ。 糸魚川の雑貨問屋へ手伝いに行って、何時の間にか店へ出るよーになった。
でも李んでーら(すももだいら)祭りの時は帰って来るということでイチさん楽しみにしていたんだーな。 誰も知らなかったがイチさー糸魚川の問屋へ荷負いに行くとき雑貨屋へチョイとよって話してたんだな、その娘と。
娘だって勤めの身で長話はできなかったろーが顔見知りのイチさーで話が合っていつか気ーゆるしてただなぁ。 そいで祭り一緒にいくことになってたらしい。
それわかったの、とっっあんと二人で荷さ負うて届けた帰りに打ち明け ただな。 帰りに茶店さ寄って娘と目くばせ何かして、暗黙の了解というのかなー。
とぶように家さ帰って握り飯つくって、とっっあんと一緒に祭りさいったさ。 とっっあんはダシに使われたんだろ。 そんでなきゃーばあさ大事な娘出すはずはねーやな。
足下明るいうちに峠こえて、そんでも来馬(クルマ地名)通ったときは暗かったそうな。 月は出ていなかったもんで真っ暗だったがローソクの灯りでミノタ橋渡るんだが板の間隔あいていて娘っこ渡るのいやがったツーこんだ。
とっっあんがローソクもって橋ゆっくり渡って、イチさ草履フトコロに入れて娘っこ負ぶって川渡ったそーな。 社(ヤシロ)に着いたらもう踊り始まってさ。 地元の世話人に祝いの金包み渡すと村の女衆が御神酒ついでくれる。 何杯のんでもかまーねぇキマリさ。
唄歌ったり、おどったり酒飲んだりで夜中までやったてーから田舎の祭り何て暢気なもんだーな。 とっっあーはけーろ(帰ろう)といったが、イチさーは酔ったとか何とか言って夜明けてから帰ると言う。
娘も夜道怖いし橋渡れないから夜明け待ってイチさと帰るって。 イチさそれほど飲んでねーのは判っているが、それはそれ気ーきかしてとっっあ一人で夜道を峠越して帰っただ。
ところが峠に差し掛かったころ、突然地響きがしてアレッ地震かなと思った瞬間、ドドドドドッカーーン………。 とおおきな音がしたそーな。 何事が起きたかわかんねーが、兎に角急いで家さ帰って寝てしもた。
夜が明けたが仕事休みだし夕べの疲れですっかり寝込んでいると表がいやに騒々しい。 どうしたかや、と思って表出て聞いて見ると山抜けだそな。
浦川の山一つ突然抜けて姫川対岸にブチ当たり下流で堰を作って上はドンドン 水が増えているという。 そんだらことと表出て姫川へ行ってみると泥水が細々と流れているだけ。
皆で様子見に行くべ、と連れだって昨日帰って来た峠越えだわ。 途中村の衆からぬけて駄菓子屋のばさまの家に寄ってみるとばさま仏壇の前に座って一生懸命拝んでこざらっしゃる。
とっっあの顔見るなり娘どしたと聞かっしやるから、昨日は遅くなって橋渡るの怖いというので李平のおばさんに頼んで泊めて貰っているハズだからこれからみてくるところだ、何だったら一緒に連れて帰るから。
「そうか是非そうしておくれ、そんなら良いけど昨日えらい音したで何事もなければよいが、ども胸騒ぎしてなんねえ。」
皆に追いついたところでハナ(先頭)のもん(者)が水で進めね、といって戻ってきた。 帰りにばあさまの所へ寄って、山抜けて水が出たので今日は橋無くて帰れねが水が引き次第帰ってくるだろと言いおいたそーな。
それから幾日かたっても水は引くどころか増え続けて下り瀬(今の奉納ブノウ橋)のあたりまで来て大きな湖(ミズウミ)になったって。 ボッカ出来ないのでみんなで下から川作って水流れるようになったのはそれから十日目。 元の姫川に戻ったのはそれから一年もしてからだとさ。
註・ これは事実で記録に寄れば明治四十四年八月八日午前一時頃、稗田山が大崩壊し浦川を埋没。 姫川東岸に激突して下流瀬戸に滞積し山を作る。行方不明 二十二人 馬一頭、牛二頭埋没とあります。
その後、釣りのついでに浦川を遡ってみましたが行けども行けども瓦礫。谷深く流れは小沢より少ない恐ろしい川でした。 上流に何とか式では日本唯一という赤い吊り橋がありましたが、ここで通行止めでした。 何の為の橋か判りませんがヒミツ基地があると言われたら納得したくなる様相です。
十日たっても娘もイチさも戻らず駄菓子屋前も通る人無く、とっっあは川造りに狩り出され心配はするものの、どうにもならなかった。 という話です。
仮橋架けて渡れるようになり、李平に行って聞いてみましたが、誰も知らない ということで、恐らく川岸で二人で寝ていて溺れたのではないかと想像するだけだったそうです。
川が渡れてボッカが通るころ、ばさまは仏壇の前に手を合わせたまま冷たくなっていました。 その後葛葉峠の下を夜通るとばさまの娘を呼ぶ声が聞こえるという噂がたって、「なんぼもらっても夜の峠越えは誰もやらね」。 ということでした。 ここでこの話はお終いです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
でも・・・と「うめ婆ちゃん」は話を続けて
実はイチさと娘は前から示し合わせていたとおり、あれから大町目指して夜道を歩き夜明けまでに「下り瀬」を過ぎて千国で山抜けを知ったそうです。 突然の出来事とは云え、とんだ道行きでした。
戻ろうとしても下り瀬まで水が来そうで危ないと聞き、そのまま大町松本と歩いて、ここで住み込みの共稼ぎをしていたということで、水が引いてから母の亡くなったたことを知り、改めて厚く弔ったそうです。
それ以後峠で娘を呼ぶ声は聞こえなくなりました。
終わり。
~清 石…≧゜ゝー<
又聞きの話ですが「おらがとっっあんの友達でよー」と語ってくれた話があります。 とっっあんの仲の良い友達でボッカやっているのがいました。 その頃のボッカは必ず二人以上で歩くのがキメ(取り決め)で、荷の少ないときはおらとこのとっっあんといつも一緒です。
ボッカの楽しみといやー(云えば)何てったって祭りだあーね。 大所のハズレで峠に掛かる所に駄菓子屋がポツンとあってな。 荷かついて峠越えて行った帰りにいつも寄って茶のんで休むところさ。
ここのば様(おばあさん)の亭主出稼ぎでけえって(帰って)こねえ。 行方知れずでさ。 娘一人あって、 器量好しだでボッカ仲間で評判で寄るもん多かった。 イチさも(イチは友達の呼び名)惚れてただーな。 その娘がさ。 糸魚川の雑貨問屋へ手伝いに行って、何時の間にか店へ出るよーになった。
でも李んでーら(すももだいら)祭りの時は帰って来るということでイチさん楽しみにしていたんだーな。 誰も知らなかったがイチさー糸魚川の問屋へ荷負いに行くとき雑貨屋へチョイとよって話してたんだな、その娘と。
娘だって勤めの身で長話はできなかったろーが顔見知りのイチさーで話が合っていつか気ーゆるしてただなぁ。 そいで祭り一緒にいくことになってたらしい。
それわかったの、とっっあんと二人で荷さ負うて届けた帰りに打ち明け ただな。 帰りに茶店さ寄って娘と目くばせ何かして、暗黙の了解というのかなー。
とぶように家さ帰って握り飯つくって、とっっあんと一緒に祭りさいったさ。 とっっあんはダシに使われたんだろ。 そんでなきゃーばあさ大事な娘出すはずはねーやな。
足下明るいうちに峠こえて、そんでも来馬(クルマ地名)通ったときは暗かったそうな。 月は出ていなかったもんで真っ暗だったがローソクの灯りでミノタ橋渡るんだが板の間隔あいていて娘っこ渡るのいやがったツーこんだ。
とっっあんがローソクもって橋ゆっくり渡って、イチさ草履フトコロに入れて娘っこ負ぶって川渡ったそーな。 社(ヤシロ)に着いたらもう踊り始まってさ。 地元の世話人に祝いの金包み渡すと村の女衆が御神酒ついでくれる。 何杯のんでもかまーねぇキマリさ。
唄歌ったり、おどったり酒飲んだりで夜中までやったてーから田舎の祭り何て暢気なもんだーな。 とっっあーはけーろ(帰ろう)といったが、イチさーは酔ったとか何とか言って夜明けてから帰ると言う。
娘も夜道怖いし橋渡れないから夜明け待ってイチさと帰るって。 イチさそれほど飲んでねーのは判っているが、それはそれ気ーきかしてとっっあ一人で夜道を峠越して帰っただ。
ところが峠に差し掛かったころ、突然地響きがしてアレッ地震かなと思った瞬間、ドドドドドッカーーン………。 とおおきな音がしたそーな。 何事が起きたかわかんねーが、兎に角急いで家さ帰って寝てしもた。
夜が明けたが仕事休みだし夕べの疲れですっかり寝込んでいると表がいやに騒々しい。 どうしたかや、と思って表出て聞いて見ると山抜けだそな。
浦川の山一つ突然抜けて姫川対岸にブチ当たり下流で堰を作って上はドンドン 水が増えているという。 そんだらことと表出て姫川へ行ってみると泥水が細々と流れているだけ。
皆で様子見に行くべ、と連れだって昨日帰って来た峠越えだわ。 途中村の衆からぬけて駄菓子屋のばさまの家に寄ってみるとばさま仏壇の前に座って一生懸命拝んでこざらっしゃる。
とっっあの顔見るなり娘どしたと聞かっしやるから、昨日は遅くなって橋渡るの怖いというので李平のおばさんに頼んで泊めて貰っているハズだからこれからみてくるところだ、何だったら一緒に連れて帰るから。
「そうか是非そうしておくれ、そんなら良いけど昨日えらい音したで何事もなければよいが、ども胸騒ぎしてなんねえ。」
皆に追いついたところでハナ(先頭)のもん(者)が水で進めね、といって戻ってきた。 帰りにばあさまの所へ寄って、山抜けて水が出たので今日は橋無くて帰れねが水が引き次第帰ってくるだろと言いおいたそーな。
それから幾日かたっても水は引くどころか増え続けて下り瀬(今の奉納ブノウ橋)のあたりまで来て大きな湖(ミズウミ)になったって。 ボッカ出来ないのでみんなで下から川作って水流れるようになったのはそれから十日目。 元の姫川に戻ったのはそれから一年もしてからだとさ。
註・ これは事実で記録に寄れば明治四十四年八月八日午前一時頃、稗田山が大崩壊し浦川を埋没。 姫川東岸に激突して下流瀬戸に滞積し山を作る。行方不明 二十二人 馬一頭、牛二頭埋没とあります。
その後、釣りのついでに浦川を遡ってみましたが行けども行けども瓦礫。谷深く流れは小沢より少ない恐ろしい川でした。 上流に何とか式では日本唯一という赤い吊り橋がありましたが、ここで通行止めでした。 何の為の橋か判りませんがヒミツ基地があると言われたら納得したくなる様相です。
十日たっても娘もイチさも戻らず駄菓子屋前も通る人無く、とっっあは川造りに狩り出され心配はするものの、どうにもならなかった。 という話です。
仮橋架けて渡れるようになり、李平に行って聞いてみましたが、誰も知らない ということで、恐らく川岸で二人で寝ていて溺れたのではないかと想像するだけだったそうです。
川が渡れてボッカが通るころ、ばさまは仏壇の前に手を合わせたまま冷たくなっていました。 その後葛葉峠の下を夜通るとばさまの娘を呼ぶ声が聞こえるという噂がたって、「なんぼもらっても夜の峠越えは誰もやらね」。 ということでした。 ここでこの話はお終いです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
でも・・・と「うめ婆ちゃん」は話を続けて
実はイチさと娘は前から示し合わせていたとおり、あれから大町目指して夜道を歩き夜明けまでに「下り瀬」を過ぎて千国で山抜けを知ったそうです。 突然の出来事とは云え、とんだ道行きでした。
戻ろうとしても下り瀬まで水が来そうで危ないと聞き、そのまま大町松本と歩いて、ここで住み込みの共稼ぎをしていたということで、水が引いてから母の亡くなったたことを知り、改めて厚く弔ったそうです。
それ以後峠で娘を呼ぶ声は聞こえなくなりました。
終わり。
~清 石…≧゜ゝー<
杉浦清石 ロマン街道塩の道 5
杉浦清石 ロマン街道塩の道 4
杉浦清石 ロマン街道塩の道 3
杉浦清石 ロマン街道塩の道 2
杉浦清石 ロマン街道塩の道 1
山男魚 「鶴見川からモントレーへ 20 完」
杉浦清石 ロマン街道塩の道 4
杉浦清石 ロマン街道塩の道 3
杉浦清石 ロマン街道塩の道 2
杉浦清石 ロマン街道塩の道 1
山男魚 「鶴見川からモントレーへ 20 完」
Posted by nakano3 at 10:25│Comments(0)
│「えんぴつ」より