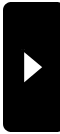2000年02月01日
杉浦清石 ロマン街道塩の道 1
95/11/24 18:11
「塩の道はロマンの道」いというタイトルで久々にこの会議室に挙げた拙文ですが私の手違いで推敲前のものを挙げてしまったので、ひどく後悔しています。
なにもあわてることはない筈なのに、なにしろ初めてのフィクションでしたので、ファイル名の原稿を間違えたようです。 どうも気になって仕方がないので、ここに改めて挙げることをお許し下さい。 清 石
「ロマン街道塩の道」
父も母も知らない私は歴史というものを拒否してきました。 親の無い子はひねくれ者。 祖先を持たない若者の選ぶ道でした。 それがいつの間にか歴史というものを受け入れられるようになったのは、渓流釣りを初めてからです。
釣り竿一本を持って木曾街道を釣り歩き、大自然の美しさと人情の細やかさを肌で感じ、より多く自然の残された東北で渓流釣りを学びました。
再度、山の美しさでは有数の、長野県の北アルプスを通る峻険な千国(チクニ)街道をベースに渓魚を求め山道をさまよい歩くうちに、いつの間にか私の心の中には祖先の我々にに残してくれた貴重な足跡(ソクセキ)という道を発見し、歴史の存在を身をもって知って親子の繋がりをも信じるようになりました。
開闊(カイカツ)な木曽谷にも「檜一本首一つ」という過酷な現実があり、狭隘な千国街道には御諏訪様(建御名方命タケミナカタノミコト)の民を思うあまねく良政が普遍 しています。 この道を歩き、地勢を目で確かめ、其の地の人にふれ言葉を聞き、そして歴史と現実を知り、いつしか親を慕う最も自然な形の人間の心を持てるようになったのは、この二本の街道・すなわち道のおかげなのです。
これから其の道の一つ千国街道を私と一緒に皆様も歩いてみませんか。
1.「岩 戸」
此の道は木曽街道のような明るさと武家政治の匂いのする派手な道ではありません。 フォッサマグナに沿う暗く厳しい道なのです。 此の道に光を当てたのは一人の男。 建御名方命(タケミナカタノミコト)でした。
彼を知るには彼の父のことから知って頂いた方が、その数奇な運命を理解するのに必要、不可欠のものなので、ここからこの物語を出発します。
彼の父は「八千矛神(ヤチホコノカミ)」と申しますが別名の大国主命(オオクニヌシノミコト)の方をご存じかと思います。 この人は因幡の白兎にも出てくる有名な人物で、福の神として誰もが知る大国様のことです。
出身は、私には時代の前後が未解決ですが、福岡県(筑前阿曇郷)の豪族、安曇(アヅミ)氏の別れではないかと仮に解釈しています。 大体安曇族は領土に支障のない海洋を活動エリアとしていて、遠くは朝鮮まで交易があり岐阜・愛知にも同族を送り込み、繁栄した種族です。
現在人口に膾炙されている卑弥呼(ヒミコ)伝説。 この人も同族で一般的には 「天照大神」という方が理解し易いでしょう。 卑弥呼は女性であるにも拘わらず武勇が優れた方で着々とその領土を伸ばして行きましたが、実は武勇よりも大変頭の良い方で美人。
韓国の方からの東方の知識も豊富。 ということはこの民族本来は海洋民族なのでした。 彼女の為なら死も厭わない男達と優れた参謀。 これを巧みに使いこなす総司令の卑弥呼。 これが各地の平定となって歴史に残るのです。
大国主も参謀の一人で若くして人望の厚かった学者です。 平定した土地の民に其の土地に合う産物を利用して交易を教え大変利益をもたらしたので、若くして福の神と崇められたのです。
各地の珍しい植物のタネや利器を袋に詰めて側から離さなかったので、一方ではあの袋の中は宝石などの貢ぎ物が入っているのでないか、と憶測し妬むものもおりました。
卑弥呼も女性です。 何人かの男の子を産みました。 しかし女の子を産んだ記録はありません。 年を取れば美貌に憧れて付いてきた男でも知力に欠けて武力に勝る者のなかでは我が国王になろうとと企(タクラ)むものもいました。
大神は「私は太陽の神である。 この太陽が姿を消すときは私の役目の終わった時であり次ぎのものに地位を譲る」と宣言をしてしまいました。 こうしておくことによって謀反の起きるのを抑圧したのです。
何故ここまで彼女が言い切ったかというと、実は彼女は懐妊していたのでした。 賢明な女でも母としての本能で、すくなくても子供を産み落とすまでは現在の地位を保っていたかったのです。
そして間もなく運命の日が来るというとき、 智者の大国主を側に呼んで、言いました。
「間もなく日の隠れる時がくるであろう。 そのときは私の命の無くなる日でもある。 命(ミコト)よ。 我が子を守っておくれ。 もしも生まれた子が女であれば私の卑弥(ヒミ)を名乗らせて欲しい」
大国主の母と共にかねて祈りの場であった洞窟に入り戸を閉めて出てきませんでした。 ここで女の子を出産したのです。 外では皆既日食がはじまりました。 この日を大神は知っていたのです。
外では大混乱。このことを大神に知らせようとする者。 大神に再び太陽を照らして貰おうと岩戸に向かって嘆願するもの。 出て貰う為に太鼓を打ち鳴らす者。後から後から集まって大騒ぎです。
しかし大神を妬む者や地位を狙う者はこれを機会に命を狙います。 ウズメノミコトは気の狂ったようにストリップを踊りだします。 これは殺気を削ぐ策略でもありました。
怪力のタジカラオノミコトが腕力で扉を開けようとしたとき、なかから大神自身が扉を開き皆の前へ出てきて両手を広げ刺客の刃を胸に受けました。 そのときの様子は西洋神のキリストのそれと酷似しているのも不思議です。
刃(ヤイバ)を受けた後広げた両手を静かに合わせると、今まで隠れていた太陽が少しずつ光をなげて大神を照らし、やがてまばゆい光をいっぱいに輝かせ、暗黒の世界を光輝に満ちた世界に変え、並み居る者、善人も悪人も皆顔を覆い、やがて慟哭の声が広がります。
この隙きに、赤子を抱いた大国主の母が民衆の中に紛れこんだのを知る人は、大国主命ただ一人でした。
2.「翡 翠」
彼自身、未知の、北の国を目指して旅立ったのは理由があります。 母と卑弥呼の娘を、すでに平定してある領土依り北の地へ行くように言ってありました。
これも大神から言われていたことで、「遥か北方に向かえば、此の地面が東西に別れるところがある。 此処にヌナという貴重な石があり、其の石が我が子を救う」 といって首に掛けていた飾りの中から日の子の表徴とも言える数個の緑色の勾玉の一つを大国主に、一つを彼の母に渡しました。
一部の暴徒に依って起きた混乱も、他の地納めに向かっていた大神の御子が帰ってきて元の静けさを取り戻したのを見てから、大国主は出発しました。名目は北方の平定ということですが、これは大神腹心の部下を排除し、引き継ぐ者が遣りやすい陣営に立て直す、体(テイ)の良い左遷をされたのです。
船を以ていきなり遠方へ行ってしまっては怪しまれるし、同行するものに刺客が居ないとは限らない。 命(ミコト)の旅は表面上はのんびりしたものでした。 何故なら、彼は武力で征することをこのまず、智と人徳で民から信頼を受けたのです。
彼の背負う大きな袋は穀物や用途の多い植物、薬草の種、それに必要な小さい道具類が入っていました。 それは正に智・仁・勇を背負っていたことになります。
行く先々で民衆に施し、教え、助ける。 それが「白兎伝説」になったり福の神として崇められる要因になりました。 彼に疑心を抱くものもなくなり、治めた地へ残るものも居て、従者こそ少なくなりましたが、口伝えで名声は高まり、彼の来るのを歓迎するようになりました。
あるときは船であるときは徒歩で、北へ北へと日本海沿岸を進みました。 気の遠くなるような長旅です。 美しい玉の有る所を聞けば胸を踊らせて歩をすすめました。 それは色彩豊かな瑪瑙である事が多く、美しくはあるが硬度で劣り、傷つき易く光をうしないます。 あまりにも堅きに過ぎると割れてしまいます。 ヌナ(翡翠)に勝るものは見つかりませんでした。
どれも透明感のある緑いろのヌナではありませんでした。 大神の首に架けられたもののように魂を吸い取られるほどの緑でそれでいて暖かみと深みを備えたあの色の玉に会いたいのです。 そこに母も居るに違いありません。
地名も場所も現在のようにハッキリしていた訳ではありません。 隣の集落まで幾日もかかるところもあり、その集落の人に聞いても玉が有るということさへ知らない所が多いのです。 長い長い年と時間が過ぎました。
ある時、いつ果てるとも知れない絶壁の脇を航海してやっとたどり着いたのが小さな浜辺でした。 小砂利を敷き詰めたような浜辺の石は色とりどりの美しい色彩で、竜宮の入り口ではないかと見まがうほどでした。 その中に緑色の半透明の混じる白い石を発見しました。 ミコトの持つ勾玉と同じ石です。
それは今の青海川(オウミガワ)河口でした。 長い絶壁の海岸は最近まで、此のアタリ随一の「親知らず・子知らず」と言われた随一の難所でした。 ここが知られていなかったのは海に面して佇立する断崖絶壁で、南の国との行き来を阻害していたからです。
この集落の人に聞いたところによると、その石を上手に玉に磨き上げる人がこの山奥に居るということでした。 早速青海川を遡り、教えられた所へ行きました。 そこは湧き水のある山の奥で、仮住まいを造り親子二人が暮らしています。
その親子というのは彼の母と大神の娘で、母は麻を流れで晒してそれを石の上に置き丸木の槌で叩いて柔らかくしています。 その流れの下では娘が黒い石でヌナを磨いています。 磨かれている方は白地に緑が流れ込んだよう微妙な模様があり、娘の手に乳白色の液体が絶えずあふれて流れていました。
「こんにちは」 声を掛けると二人は驚いた様子もなく、作業の手を休めて会釈を返します。 まるでミコトが来るのを予知していたようでした。
山の中に長く棲むと遥か下から上がってくる足音に気付き、娘が敵意のない人と判断をしていたのです。 或いは命(ミコト)のことを母から聞いていたのかも知れません。
それより驚いたのは命(ミコト)の方です。 振り返って会釈した娘の美しいこと。 色は抜けるように白く、今磨がかれている翡翠の白。 鼻も高からず低からず、ミコトの今まで出会った南方系の浅黒い肌と違ってまるで異国の人でした。
作業衣なのでしょうが里のそれと異なり、良く晒してあります。 チラッとのぞく胸のあたりの白さは芳(カグワ)しい香りさえ漂うような素肌です。
命(ミコト)の胸の鼓動が高まり娘に聞こえるのではないかと顔に血の気がのぼります。
俗に言う一目惚れです。 もう声を掛けたところから一歩も動けまん。 身体じゅうに電流が流れ声も出ません。 先に声を掛けたのは娘の方でした。
実はこの娘、ここから糸魚川に掛けて女王様のように慕われていて、糸魚川の屋敷に帰れば、漁師は魚を、農民は穀物を、狩り人は獣(ケモノ)の肉をささげます。 これはこの親子が南の方から持ってきた衣料になる麻や農作物などをこのあたりの住民に与え指導して、僻地にもかかわらず、豊かに暮らせるようになったからです。
「何しにいらしたの」 娘はこの男が、かねてから聞いていた母の息子ということは、わかっていました。 狩りや漁の格好ではないし大きな袋を肩にしています。 澄んだ目をみれば敵意のないことも知性豊かな人であることも察せられます。
大昔の人間は今のように話せば判るのではなく、見ただけで敵意があるかどうかを判別する能力をそなえています。 歩く音で獣か人かの区別がつきますし、流れの音や風の向きや湿度で明日の晴雨を知り木のざわめきで天変地異を予測出来ます。 大自然の話し声が聞き分けられるのです。 流れの音にも邪魔されずに近ずくものが判り、またそうでなくてはこの山奥で生きては行けません。
「あのー 玉を磨くのを見たいんです」 取って付けたように答えた彼の心を読みとるように、「もうじき仕上がりますからどうぞご覧になって。 終わったら家へ帰りますけど糸魚川までご一緒します?」
母親の顔と男の顔と見比べながらいいます。 どうせ彼は着いて来るに違いな いと感じとり、母に目で相談していたのです。 「ハア、出来れば。 それにお願いもありますので」
やっと落ち着きを取り戻した大国主命は我に返りましたが、それでもまだ視線は娘に注がれて返事も半分上の空です。
3.「御諏訪様」
娘は「奴奈川比売(ヌナカワヒメ)」と呼ばれていました。 ヌナというのは翡翠のことで、今の姫川も昔は奴奈川(又は沼川・読みは同じヌナカワ)で翡翠の川 という意味です。 後世 比売の方を採って今の姫川になりました。 比売というのは卑弥呼の卑弥と同意語で呼は愛称、今の子と同じです。
大国主命(オオクニヌシノミコト)は糸魚川の姫(ヌナカワヒメ)の家に居候をしているうちにお互いに違う知識を豊富に持つことを知り、未知への憧れ(アコガレ)と才能に当然のように、足らざるものと、なり余れる物との接触で夫婦になったのは言うまでもありません。
大国主命は翡翠の勾玉と美人妻を手に入れて暫し故郷も忘れ、有頂天になっているうちに男の子が誕生しました。 この子は立派な若者に育ち父と母の才を受け継ぎ、お父さん以上に才能を持ち将来は立派な領主になるであろうと、民衆に慕われるようになりました。 名前は建御名方命(タケミナカタノミコト)と申します。
元々南方の人である大国主命は、いつしかこのあたりも自分の領土である、という意識があるため、自分より知力の勝る息子の評判の良さが少し面白くありません。 それである時息子に「ここは俺の領土だぞ」とダメ押しの宣言をしました。
「いやお父さん違うよ。 お父さんは他所(ヨソ)から来てお母さんの領土に入った言うなれば婿養子でしょ。 お母さんの土地は私が継ぐのが筋じゃありませんか」。
本当なら身分が違うといわれても仕方が無いのです。 こんなことから親子喧嘩がはじまったのです。
この親子喧嘩はとどまることを知らず、ついに戦にまで発展してしましまったのです。 父親の大国主は南方へ援軍を頼む。 領民の信頼は有るとは云え青年の建御名方命の方に付く軍勢は知れた物。 当然敗北です。 それでも子供の頃から この地で育った彼は年取った父より地理に明るく、姫川を遡って退却します。
今のように街道がある訳ではないので山の中を姫川上流に向かって逃げました。 この頃の戦いは大軍を率いてドッと攻め込むなんていうことは出来はしない。 何人もの者が固まって攻める道というものが無かったのです。 山の中に入ってしまえば追いかけることもできません。
建御名方命は慌てて逃げることもなく、行く先々で郷の衆(土地の人)に色々生活(クラシ)の足しになることを教えてゆきました。 荒れ地を開墾して麻の種を撒き麻を作ること、それを打って柔らかくして縄や網を作ること。
動物が集まって飲む水には塩分が含まれているので濃縮して野菜の保存ができること。 温泉・冷泉が病を癒すこと。等多くの生活に役立つことを教えたりして、割にのんびりした逃避行でした。
喧嘩してもそこは親子、たいして追撃もしなかったとみえます。 道々良政を施しながら諏訪湖にまで来て、ここに安住の地を見出しました。 そして御諏訪様と言われて今は全国の諏訪神社に祀られるほど慕われています。
諏訪大社下社秋の宮には正面に建御名方命、右手に母の奴奈川比売が祀ってあり姫の方の社には底のない柄杓が沢山奉納してあります。 これは姫にあやかって安産を願う善女が奉納したものです。
それとは別に奴奈河比売を主神とする社は糸魚川海岸寄りの道を名立に向かって進むんだところにあり姫と御諏訪様親子の像も糸魚川市内にあります。 大国主命の方はその後の消息はわかりませんが、大黒様になって貴方の近くに 居て庶民に福を授けて下さっているのでしょう。
~清 石…≧゜ゝー<
「塩の道はロマンの道」いというタイトルで久々にこの会議室に挙げた拙文ですが私の手違いで推敲前のものを挙げてしまったので、ひどく後悔しています。
なにもあわてることはない筈なのに、なにしろ初めてのフィクションでしたので、ファイル名の原稿を間違えたようです。 どうも気になって仕方がないので、ここに改めて挙げることをお許し下さい。 清 石
「ロマン街道塩の道」
父も母も知らない私は歴史というものを拒否してきました。 親の無い子はひねくれ者。 祖先を持たない若者の選ぶ道でした。 それがいつの間にか歴史というものを受け入れられるようになったのは、渓流釣りを初めてからです。
釣り竿一本を持って木曾街道を釣り歩き、大自然の美しさと人情の細やかさを肌で感じ、より多く自然の残された東北で渓流釣りを学びました。
再度、山の美しさでは有数の、長野県の北アルプスを通る峻険な千国(チクニ)街道をベースに渓魚を求め山道をさまよい歩くうちに、いつの間にか私の心の中には祖先の我々にに残してくれた貴重な足跡(ソクセキ)という道を発見し、歴史の存在を身をもって知って親子の繋がりをも信じるようになりました。
開闊(カイカツ)な木曽谷にも「檜一本首一つ」という過酷な現実があり、狭隘な千国街道には御諏訪様(建御名方命タケミナカタノミコト)の民を思うあまねく良政が普遍 しています。 この道を歩き、地勢を目で確かめ、其の地の人にふれ言葉を聞き、そして歴史と現実を知り、いつしか親を慕う最も自然な形の人間の心を持てるようになったのは、この二本の街道・すなわち道のおかげなのです。
これから其の道の一つ千国街道を私と一緒に皆様も歩いてみませんか。
1.「岩 戸」
此の道は木曽街道のような明るさと武家政治の匂いのする派手な道ではありません。 フォッサマグナに沿う暗く厳しい道なのです。 此の道に光を当てたのは一人の男。 建御名方命(タケミナカタノミコト)でした。
彼を知るには彼の父のことから知って頂いた方が、その数奇な運命を理解するのに必要、不可欠のものなので、ここからこの物語を出発します。
彼の父は「八千矛神(ヤチホコノカミ)」と申しますが別名の大国主命(オオクニヌシノミコト)の方をご存じかと思います。 この人は因幡の白兎にも出てくる有名な人物で、福の神として誰もが知る大国様のことです。
出身は、私には時代の前後が未解決ですが、福岡県(筑前阿曇郷)の豪族、安曇(アヅミ)氏の別れではないかと仮に解釈しています。 大体安曇族は領土に支障のない海洋を活動エリアとしていて、遠くは朝鮮まで交易があり岐阜・愛知にも同族を送り込み、繁栄した種族です。
現在人口に膾炙されている卑弥呼(ヒミコ)伝説。 この人も同族で一般的には 「天照大神」という方が理解し易いでしょう。 卑弥呼は女性であるにも拘わらず武勇が優れた方で着々とその領土を伸ばして行きましたが、実は武勇よりも大変頭の良い方で美人。
韓国の方からの東方の知識も豊富。 ということはこの民族本来は海洋民族なのでした。 彼女の為なら死も厭わない男達と優れた参謀。 これを巧みに使いこなす総司令の卑弥呼。 これが各地の平定となって歴史に残るのです。
大国主も参謀の一人で若くして人望の厚かった学者です。 平定した土地の民に其の土地に合う産物を利用して交易を教え大変利益をもたらしたので、若くして福の神と崇められたのです。
各地の珍しい植物のタネや利器を袋に詰めて側から離さなかったので、一方ではあの袋の中は宝石などの貢ぎ物が入っているのでないか、と憶測し妬むものもおりました。
卑弥呼も女性です。 何人かの男の子を産みました。 しかし女の子を産んだ記録はありません。 年を取れば美貌に憧れて付いてきた男でも知力に欠けて武力に勝る者のなかでは我が国王になろうとと企(タクラ)むものもいました。
大神は「私は太陽の神である。 この太陽が姿を消すときは私の役目の終わった時であり次ぎのものに地位を譲る」と宣言をしてしまいました。 こうしておくことによって謀反の起きるのを抑圧したのです。
何故ここまで彼女が言い切ったかというと、実は彼女は懐妊していたのでした。 賢明な女でも母としての本能で、すくなくても子供を産み落とすまでは現在の地位を保っていたかったのです。
そして間もなく運命の日が来るというとき、 智者の大国主を側に呼んで、言いました。
「間もなく日の隠れる時がくるであろう。 そのときは私の命の無くなる日でもある。 命(ミコト)よ。 我が子を守っておくれ。 もしも生まれた子が女であれば私の卑弥(ヒミ)を名乗らせて欲しい」
大国主の母と共にかねて祈りの場であった洞窟に入り戸を閉めて出てきませんでした。 ここで女の子を出産したのです。 外では皆既日食がはじまりました。 この日を大神は知っていたのです。
外では大混乱。このことを大神に知らせようとする者。 大神に再び太陽を照らして貰おうと岩戸に向かって嘆願するもの。 出て貰う為に太鼓を打ち鳴らす者。後から後から集まって大騒ぎです。
しかし大神を妬む者や地位を狙う者はこれを機会に命を狙います。 ウズメノミコトは気の狂ったようにストリップを踊りだします。 これは殺気を削ぐ策略でもありました。
怪力のタジカラオノミコトが腕力で扉を開けようとしたとき、なかから大神自身が扉を開き皆の前へ出てきて両手を広げ刺客の刃を胸に受けました。 そのときの様子は西洋神のキリストのそれと酷似しているのも不思議です。
刃(ヤイバ)を受けた後広げた両手を静かに合わせると、今まで隠れていた太陽が少しずつ光をなげて大神を照らし、やがてまばゆい光をいっぱいに輝かせ、暗黒の世界を光輝に満ちた世界に変え、並み居る者、善人も悪人も皆顔を覆い、やがて慟哭の声が広がります。
この隙きに、赤子を抱いた大国主の母が民衆の中に紛れこんだのを知る人は、大国主命ただ一人でした。
2.「翡 翠」
彼自身、未知の、北の国を目指して旅立ったのは理由があります。 母と卑弥呼の娘を、すでに平定してある領土依り北の地へ行くように言ってありました。
これも大神から言われていたことで、「遥か北方に向かえば、此の地面が東西に別れるところがある。 此処にヌナという貴重な石があり、其の石が我が子を救う」 といって首に掛けていた飾りの中から日の子の表徴とも言える数個の緑色の勾玉の一つを大国主に、一つを彼の母に渡しました。
一部の暴徒に依って起きた混乱も、他の地納めに向かっていた大神の御子が帰ってきて元の静けさを取り戻したのを見てから、大国主は出発しました。名目は北方の平定ということですが、これは大神腹心の部下を排除し、引き継ぐ者が遣りやすい陣営に立て直す、体(テイ)の良い左遷をされたのです。
船を以ていきなり遠方へ行ってしまっては怪しまれるし、同行するものに刺客が居ないとは限らない。 命(ミコト)の旅は表面上はのんびりしたものでした。 何故なら、彼は武力で征することをこのまず、智と人徳で民から信頼を受けたのです。
彼の背負う大きな袋は穀物や用途の多い植物、薬草の種、それに必要な小さい道具類が入っていました。 それは正に智・仁・勇を背負っていたことになります。
行く先々で民衆に施し、教え、助ける。 それが「白兎伝説」になったり福の神として崇められる要因になりました。 彼に疑心を抱くものもなくなり、治めた地へ残るものも居て、従者こそ少なくなりましたが、口伝えで名声は高まり、彼の来るのを歓迎するようになりました。
あるときは船であるときは徒歩で、北へ北へと日本海沿岸を進みました。 気の遠くなるような長旅です。 美しい玉の有る所を聞けば胸を踊らせて歩をすすめました。 それは色彩豊かな瑪瑙である事が多く、美しくはあるが硬度で劣り、傷つき易く光をうしないます。 あまりにも堅きに過ぎると割れてしまいます。 ヌナ(翡翠)に勝るものは見つかりませんでした。
どれも透明感のある緑いろのヌナではありませんでした。 大神の首に架けられたもののように魂を吸い取られるほどの緑でそれでいて暖かみと深みを備えたあの色の玉に会いたいのです。 そこに母も居るに違いありません。
地名も場所も現在のようにハッキリしていた訳ではありません。 隣の集落まで幾日もかかるところもあり、その集落の人に聞いても玉が有るということさへ知らない所が多いのです。 長い長い年と時間が過ぎました。
ある時、いつ果てるとも知れない絶壁の脇を航海してやっとたどり着いたのが小さな浜辺でした。 小砂利を敷き詰めたような浜辺の石は色とりどりの美しい色彩で、竜宮の入り口ではないかと見まがうほどでした。 その中に緑色の半透明の混じる白い石を発見しました。 ミコトの持つ勾玉と同じ石です。
それは今の青海川(オウミガワ)河口でした。 長い絶壁の海岸は最近まで、此のアタリ随一の「親知らず・子知らず」と言われた随一の難所でした。 ここが知られていなかったのは海に面して佇立する断崖絶壁で、南の国との行き来を阻害していたからです。
この集落の人に聞いたところによると、その石を上手に玉に磨き上げる人がこの山奥に居るということでした。 早速青海川を遡り、教えられた所へ行きました。 そこは湧き水のある山の奥で、仮住まいを造り親子二人が暮らしています。
その親子というのは彼の母と大神の娘で、母は麻を流れで晒してそれを石の上に置き丸木の槌で叩いて柔らかくしています。 その流れの下では娘が黒い石でヌナを磨いています。 磨かれている方は白地に緑が流れ込んだよう微妙な模様があり、娘の手に乳白色の液体が絶えずあふれて流れていました。
「こんにちは」 声を掛けると二人は驚いた様子もなく、作業の手を休めて会釈を返します。 まるでミコトが来るのを予知していたようでした。
山の中に長く棲むと遥か下から上がってくる足音に気付き、娘が敵意のない人と判断をしていたのです。 或いは命(ミコト)のことを母から聞いていたのかも知れません。
それより驚いたのは命(ミコト)の方です。 振り返って会釈した娘の美しいこと。 色は抜けるように白く、今磨がかれている翡翠の白。 鼻も高からず低からず、ミコトの今まで出会った南方系の浅黒い肌と違ってまるで異国の人でした。
作業衣なのでしょうが里のそれと異なり、良く晒してあります。 チラッとのぞく胸のあたりの白さは芳(カグワ)しい香りさえ漂うような素肌です。
命(ミコト)の胸の鼓動が高まり娘に聞こえるのではないかと顔に血の気がのぼります。
俗に言う一目惚れです。 もう声を掛けたところから一歩も動けまん。 身体じゅうに電流が流れ声も出ません。 先に声を掛けたのは娘の方でした。
実はこの娘、ここから糸魚川に掛けて女王様のように慕われていて、糸魚川の屋敷に帰れば、漁師は魚を、農民は穀物を、狩り人は獣(ケモノ)の肉をささげます。 これはこの親子が南の方から持ってきた衣料になる麻や農作物などをこのあたりの住民に与え指導して、僻地にもかかわらず、豊かに暮らせるようになったからです。
「何しにいらしたの」 娘はこの男が、かねてから聞いていた母の息子ということは、わかっていました。 狩りや漁の格好ではないし大きな袋を肩にしています。 澄んだ目をみれば敵意のないことも知性豊かな人であることも察せられます。
大昔の人間は今のように話せば判るのではなく、見ただけで敵意があるかどうかを判別する能力をそなえています。 歩く音で獣か人かの区別がつきますし、流れの音や風の向きや湿度で明日の晴雨を知り木のざわめきで天変地異を予測出来ます。 大自然の話し声が聞き分けられるのです。 流れの音にも邪魔されずに近ずくものが判り、またそうでなくてはこの山奥で生きては行けません。
「あのー 玉を磨くのを見たいんです」 取って付けたように答えた彼の心を読みとるように、「もうじき仕上がりますからどうぞご覧になって。 終わったら家へ帰りますけど糸魚川までご一緒します?」
母親の顔と男の顔と見比べながらいいます。 どうせ彼は着いて来るに違いな いと感じとり、母に目で相談していたのです。 「ハア、出来れば。 それにお願いもありますので」
やっと落ち着きを取り戻した大国主命は我に返りましたが、それでもまだ視線は娘に注がれて返事も半分上の空です。
3.「御諏訪様」
娘は「奴奈川比売(ヌナカワヒメ)」と呼ばれていました。 ヌナというのは翡翠のことで、今の姫川も昔は奴奈川(又は沼川・読みは同じヌナカワ)で翡翠の川 という意味です。 後世 比売の方を採って今の姫川になりました。 比売というのは卑弥呼の卑弥と同意語で呼は愛称、今の子と同じです。
大国主命(オオクニヌシノミコト)は糸魚川の姫(ヌナカワヒメ)の家に居候をしているうちにお互いに違う知識を豊富に持つことを知り、未知への憧れ(アコガレ)と才能に当然のように、足らざるものと、なり余れる物との接触で夫婦になったのは言うまでもありません。
大国主命は翡翠の勾玉と美人妻を手に入れて暫し故郷も忘れ、有頂天になっているうちに男の子が誕生しました。 この子は立派な若者に育ち父と母の才を受け継ぎ、お父さん以上に才能を持ち将来は立派な領主になるであろうと、民衆に慕われるようになりました。 名前は建御名方命(タケミナカタノミコト)と申します。
元々南方の人である大国主命は、いつしかこのあたりも自分の領土である、という意識があるため、自分より知力の勝る息子の評判の良さが少し面白くありません。 それである時息子に「ここは俺の領土だぞ」とダメ押しの宣言をしました。
「いやお父さん違うよ。 お父さんは他所(ヨソ)から来てお母さんの領土に入った言うなれば婿養子でしょ。 お母さんの土地は私が継ぐのが筋じゃありませんか」。
本当なら身分が違うといわれても仕方が無いのです。 こんなことから親子喧嘩がはじまったのです。
この親子喧嘩はとどまることを知らず、ついに戦にまで発展してしましまったのです。 父親の大国主は南方へ援軍を頼む。 領民の信頼は有るとは云え青年の建御名方命の方に付く軍勢は知れた物。 当然敗北です。 それでも子供の頃から この地で育った彼は年取った父より地理に明るく、姫川を遡って退却します。
今のように街道がある訳ではないので山の中を姫川上流に向かって逃げました。 この頃の戦いは大軍を率いてドッと攻め込むなんていうことは出来はしない。 何人もの者が固まって攻める道というものが無かったのです。 山の中に入ってしまえば追いかけることもできません。
建御名方命は慌てて逃げることもなく、行く先々で郷の衆(土地の人)に色々生活(クラシ)の足しになることを教えてゆきました。 荒れ地を開墾して麻の種を撒き麻を作ること、それを打って柔らかくして縄や網を作ること。
動物が集まって飲む水には塩分が含まれているので濃縮して野菜の保存ができること。 温泉・冷泉が病を癒すこと。等多くの生活に役立つことを教えたりして、割にのんびりした逃避行でした。
喧嘩してもそこは親子、たいして追撃もしなかったとみえます。 道々良政を施しながら諏訪湖にまで来て、ここに安住の地を見出しました。 そして御諏訪様と言われて今は全国の諏訪神社に祀られるほど慕われています。
諏訪大社下社秋の宮には正面に建御名方命、右手に母の奴奈川比売が祀ってあり姫の方の社には底のない柄杓が沢山奉納してあります。 これは姫にあやかって安産を願う善女が奉納したものです。
それとは別に奴奈河比売を主神とする社は糸魚川海岸寄りの道を名立に向かって進むんだところにあり姫と御諏訪様親子の像も糸魚川市内にあります。 大国主命の方はその後の消息はわかりませんが、大黒様になって貴方の近くに 居て庶民に福を授けて下さっているのでしょう。
~清 石…≧゜ゝー<
杉浦清石 ロマン街道塩の道 6
杉浦清石 ロマン街道塩の道 5
杉浦清石 ロマン街道塩の道 4
杉浦清石 ロマン街道塩の道 3
杉浦清石 ロマン街道塩の道 2
山男魚 「鶴見川からモントレーへ 20 完」
杉浦清石 ロマン街道塩の道 5
杉浦清石 ロマン街道塩の道 4
杉浦清石 ロマン街道塩の道 3
杉浦清石 ロマン街道塩の道 2
山男魚 「鶴見川からモントレーへ 20 完」
Posted by nakano3 at 21:21│Comments(0)
│「えんぴつ」より